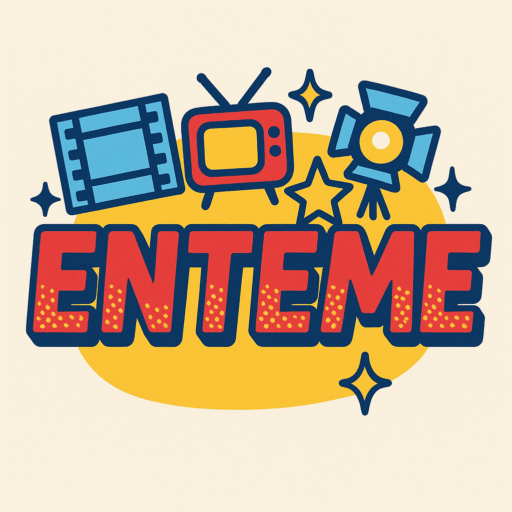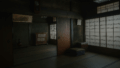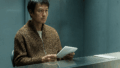「たった2人の兵士が、終戦を知らずに木の上で2年間も生き延びていた」――そんな信じがたい実話が、今、映画『木の上の軍隊』として私たちの前に甦ります。
本作は、太平洋戦争末期の沖縄・伊江島を舞台に、極限状態の中で命をつなぎ、生き抜いた男たちの姿を描いた衝撃の物語です。単なる戦争映画ではなく、命の尊さ、仲間との絆、そして平和への祈りが込められた人間ドラマとして、観る者の心を深く揺さぶります。
実際に存在した2人の兵士をモデルに、戦争の理不尽さと、それでもなお希望を捨てなかった人間の強さを描いたこの作品は、終戦80年という節目に公開されたことでも大きな注目を集めています。
この記事では、映画の背景やあらすじ、モデルとなった人物、そして舞台との違いや現在の伊江島の様子までを徹底解説。戦争を知らない世代にも「平和とは何か」を問いかける、心に残る一本を深く掘り下げていきます。
映画『木の上の軍隊』とは?基本情報と作品概要
映画『木の上の軍隊』は、太平洋戦争末期の沖縄・伊江島で実際に起きた出来事をもとに、2人の日本兵が終戦を知らずにガジュマルの木の上で約2年間生き延びたという実話を描いた作品です。戦争の極限状況の中で人間が見せる葛藤やユーモア、そして平和への願いを繊細に描き出しています。
原作は、劇作家・井上ひさし氏が構想した戯曲『木の上の軍隊』。こまつ座による舞台作品としても人気を博し、2025年には堤真一と山田裕貴のW主演で映画化されました。
以下に、映画の基本情報を表でまとめました。
| タイトル | 木の上の軍隊 |
|---|---|
| 公開年 | 2025年(沖縄先行:6月13日/全国公開:7月25日) |
| 監督 | 平一紘 |
| 主演 | 堤真一(山下一雄少尉役)、山田裕貴(安慶名セイジュン役) |
| 原作 | 井上ひさし(舞台戯曲『木の上の軍隊』) |
| 製作 | 映画「木の上の軍隊」製作委員会 |
| 主題歌 | 「ニヌファブシ」/Anly(伊江島出身) |
本作は、戦争映画でありながら「巻き込まれる側」の視点に立ち、ユーモアと人間味を交えながら命の尊さや希望を描いた異色の作品として注目を集めています。また、終戦80周年という節目に公開されたことから、教育的・平和啓発的な意味合いも強く持っています。
【あらすじ】2人の兵士が木の上で過ごした衝撃の2年間
映画『木の上の軍隊』の舞台は、1945年の沖縄県伊江島。米軍の激しい空爆と上陸により、島は壊滅的な状況に陥ります。その混乱の中で、日本軍の少尉・山下一雄と新兵・安慶名セイジュンは敵の追撃から逃れ、巨大なガジュマルの木の上に身を隠します。彼らは終戦を知らず、そのまま約2年間を樹上で過ごすという異例の生活を送ることになります。
以下に、物語の構成と主な出来事をまとめました。
| 時期 | 出来事 |
|---|---|
| 1945年4月 | 伊江島に米軍上陸。山下と安慶名が壕から逃れ、木の上へ避難。 |
| 1945年〜1947年 | 援軍を待ち続けるが連絡手段なし。残飯や野菜で命をつなぐ。木の上で巣をつくり生活。 |
| 途中 | 飢えと病に苦しみながらも、互いに支え合う。米兵の物資を活用し、戦争が続いていると信じ続ける。 |
| 1947年3月 | 終戦を知り、ようやく木を降りて捕虜として保護される。 |
物語の核心は、「終戦を知らずに孤立した兵士がどのように生き延びたか」というサバイバルの記録でありながら、その中で芽生える人間性や希望、矛盾、葛藤に焦点が当てられています。
2人は立場も性格も異なり、しばしば衝突しますが、長い時間を共に過ごすうちに、少しずつ理解し合い、連帯感を築いていきます。戦争の狂気に巻き込まれた者たちの姿を、ユーモラスかつ哀切に描いた本作は、「生きるとは何か?」という根源的な問いを観る者に投げかけてきます。
【実話】モデルとなった兵士たちの真実の物語
映画『木の上の軍隊』はフィクションのように思えるかもしれませんが、実はこの物語には明確な実話のモデルが存在します。モデルとなったのは、第二次世界大戦末期に沖縄県伊江島で実際にガジュマルの木の上に2年間身を潜め、生き延びた2人の日本兵です。
以下は、彼らの基本情報と実際に体験したエピソードをまとめた表です。
| 氏名 | 出身地 | 役柄のモデル | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 山口静雄 | 宮崎県小林市 | 山下一雄(堤真一) | 厳格で規律に忠実。戦後は故郷に戻り、家族に戦争体験を伝えた。 |
| 佐次田秀順 | 沖縄県うるま市 | 安慶名セイジュン(山田裕貴) | 地元出身の新兵。島の知識を活かして生存に貢献。戦後も沖縄で暮らした。 |
彼らは、1945年4月の米軍上陸後に戦闘を逃れ、伊江島の「ニーバンガジィマール」と呼ばれるガジュマルの木の上に避難。そこで2年間、援軍を信じ、終戦を知らぬまま生活を続けました。生活は過酷を極め、ハブに噛まれたり、台風に襲われたりする中、米兵の残飯や野菜、雨水などで命をつないだとされています。
さらに驚くべきは、彼らが「亡霊になった兵士」と偽って島民と手紙のやり取りをしていたという点です。この交流により、戦争がすでに終わっていることを知るきっかけとなりました。
彼らの体験は戦争の悲惨さと同時に、人間の生き抜く力や知恵、そして希望を象徴する出来事として、現代に語り継がれています。
【その後】戦後の人生と子孫たちの再会エピソード

画像はイメージです
映画『木の上の軍隊』の実話モデルとなった山口静雄さんと佐次田秀順さんは、過酷な樹上生活を経て1947年に保護されました。終戦を知らぬまま2年間も木の上で過ごした2人は、その後それぞれの地元に戻り、戦後の人生を歩むことになります。
以下に2人の戦後の歩みと家族の再会に関するエピソードをまとめた表を示します。
| 人物 | 戦後の生活 | 家族とのつながり | 再会エピソード |
|---|---|---|---|
| 山口静雄 | 宮崎県で家庭を築き、子どもに戦争体験を伝える | 次男・輝人さん、三女・春子さんらが体験を受け継ぐ | 2024年11月、伊江島で佐次田家と対面。父の足跡に感謝を捧げた |
| 佐次田秀順 | 沖縄県うるま市で生活。島の平和活動に関与 | 長男・勉さん、次男・満さんが当時の話を証言 | 山口家と初対面し、父たちの記憶を共有。「命をつないだ木」に手を合わせた |
この再会は、映画『木の上の軍隊』の制作をきっかけに実現しました。80年近くの時を経て、モデルとなった2人の家族が実際に伊江島のガジュマルの木の前で顔を合わせたことは、単なる偶然ではなく、平和の象徴としての意味を帯びています。
再会の場で語られた言葉には、「父がこの木で命をつないでくれたから、私たちが今ここにいる」という感謝と誇りが込められていました。これは、戦争が個人と家族に与える影響の大きさを改めて示すものでもあります。
2人の兵士の“その後”は、単なる歴史ではなく、今を生きる私たちにとっての「平和の大切さ」を再確認させてくれる貴重なメッセージです。
舞台と映画の違い|原作の魅力と映像化の意義
『木の上の軍隊』は、もともと劇作家・井上ひさしが構想した舞台作品として誕生しました。1990年代から構想されていた本作は、井上氏の死後、こまつ座によって2013年に舞台化され、2025年には映画として映像化されました。同じ原案ながら、舞台と映画では表現方法や演出、訴求力に明確な違いがあります。
以下に舞台版と映画版の違いを比較した表を示します。
| 項目 | 舞台版 | 映画版 |
|---|---|---|
| 初演 | 2013年(こまつ座) | 2025年全国公開(沖縄先行) |
| 演出の特徴 | 限られた空間の中で俳優の台詞と演技が主役 | 実地ロケによるリアリズム。映像・音響・自然描写で臨場感を演出 |
| 主な俳優 | 藤原竜也、山西惇など | 堤真一、山田裕貴 |
| 表現スタイル | 会話劇中心。心理描写や間の取り方に重点 | 映像を活用し、空気感・自然・戦場のリアルを視覚で伝える |
| 平和へのメッセージ | 観客に語りかける形式で、反戦と生きる力を強調 | 映像と音楽を通じてより広い世代に感情を届ける |
舞台版の魅力は、極限状態にある2人の心の揺れを、観客との“距離の近さ”で感じられる点です。限られた舞台空間で、言葉の重みと間の演出が際立ち、観客は登場人物と同じ空間にいるような緊張感を味わえます。
一方、映画版では伊江島でのロケを通じて、実際のガジュマルの木や戦地の様子をリアルに映し出しています。土や風の匂い、虫の音、空の色までもが画面に反映され、より臨場感あふれる体験が可能です。また、若い世代にも届きやすい映像媒体としてのメリットを活かし、「知らない戦争」を伝える力があります。
映像化の意義は、戦争体験の風化を防ぎ、平和への想いを現代社会に広めることです。とくに2025年の終戦80年に合わせて公開された本作は、歴史の節目に立つ今、あらためて「平和とは何か」を問い直す強いメッセージ性を帯びています。
ガジュマルの木「ニーバンガジィマール」の現在
『木の上の軍隊』の舞台となったガジュマルの木は、沖縄県伊江島に実在します。この木は「ニーバンガジィマール」と呼ばれ、物語のモデルとなった2人の兵士が約2年間身を潜めていた場所です。現在もその木は保存されており、伊江島の平和の象徴として多くの人々に語り継がれています。
「ニーバンガジィマール」はただの木ではなく、「命を救った神木」として特別な意味を持っています。以下にその現在の状況と取り組みをまとめます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県伊江島・宮城家の屋敷跡 |
| 名称の由来 | 「ニーバン」は屋号、「ガジィマール」はガジュマルの方言 |
| 戦後の扱い | 平和の象徴として地元住民に大切に保管 |
| 保存状況 | 2023年の台風で倒木→土を入れ替え支柱を強化して再建 |
| 訪問者 | 遺族や観光客、修学旅行生などが多数訪れる |
特に注目すべきは、2023年の台風6号で一度倒木してしまったものの、地域住民と専門家の手により再生された点です。新たに支柱を設置し、根の周囲に新たな土を入れることで、木の再生が図られました。
2024年11月には、実話のモデルとなった山口静雄さんと佐次田秀順さんの遺族がこの木を訪問し、「父たちの命をつないだ場所」として手を合わせる姿が報道され、多くの人の感動を呼びました。
現在、「ニーバンガジィマール」は単なる戦争遺構ではなく、戦争の記憶を風化させないための教育資源としても活用されています。伊江島を訪れる多くの修学旅行生に対して、この木を通じた平和教育が行われており、「過去の戦争を学び、未来の平和を考える」場となっています。
『木の上の軍隊』が伝える平和へのメッセージ
映画『木の上の軍隊』は、単なる戦争映画ではありません。この作品が伝える本質的なメッセージは「平和の尊さ」と「命の奇跡」です。実話をベースにした物語は、極限状態で生き延びた2人の兵士の姿を通じて、現代の私たちに深い問いかけを投げかけています。
以下に、この作品が伝える主な平和へのメッセージを整理します。
| メッセージ | 作品での描写 |
|---|---|
| 命の尊さ | 2年間、木の上で生き抜いた兵士の姿は「生きること」そのものの尊さを物語る |
| 戦争の理不尽さ | 終戦を知らず、無意味な潜伏を強いられた事実が、戦争の無情さを浮き彫りに |
| 異文化理解と共存 | 敵国の残飯に命を救われる描写が、国境や敵味方を超えた人間の本質を示す |
| 次世代への継承 | 遺族によるガジュマル訪問や伊江島での平和学習を通じ、歴史の記憶が次代に引き継がれる |
特に、主人公たちが「死ぬのを待つだけの生活」から「生きるための工夫」に転じていく描写は、戦争という過酷な現実の中にも希望とユーモアがあることを教えてくれます。これは、悲惨な戦争の中にも人間らしさを忘れない精神性の象徴ともいえます。
さらに、映画の舞台となった伊江島では、実際にガジュマルの木の保存や平和学習が進められており、戦争の教訓を地域ぐるみで後世に伝えようとする努力が続いています。
主演の堤真一は「この作品が、戦争を知らない世代に“生きることの意味”を問いかけるきっかけになれば」と語り、山田裕貴も「平和な日常がどれほど貴重かを伝えたい」とコメントしています。
『木の上の軍隊』は、終戦80年という節目において、過去の記憶を風化させず、未来への教訓として活かすための強いメッセージを放っています。戦争を描くのではなく、「なぜ戦争があってはならないのか」を語るための映画。それがこの作品の本質です。
まとめ|『木の上の軍隊』が私たちに問いかけるもの

画像はイメージです
- 実話に基づく感動の物語:太平洋戦争末期、2人の日本兵が終戦を知らずに2年間を木の上で生き延びたという実話をもとに構成。
- 極限状況下の人間ドラマ:飢えや孤独、対立を乗り越えながらも、希望と連帯感を育む姿をユーモアを交えて描写。
- モデルとなった兵士の証言と家族の絆:戦後も地元で平和活動に関わり、子孫同士の再会が「命の継承」として大きな意味を持つ。
- 舞台版との対比でわかる映像化の意義:舞台は言葉と心理、映画は映像と自然描写によって、異なる形で平和のメッセージを伝える。
- 実在の「ニーバンガジィマール」:兵士が身を潜めた木は現在も保存され、平和教育の現場として活用されている。
- 多層的な平和メッセージ:
- 命の尊さを描き出す生存劇
- 戦争の理不尽さを訴える実話性
- 文化や立場を超えた共感と共存の視点
- 次世代への記憶継承の重要性
- 終戦80年という節目の意義:記憶の風化を防ぎ、「なぜ戦争をしてはならないのか」という問いを現代に届ける役割を担う。